2011-12-25 [長年日記]
_ [Jazz] アイク・デイの伝説
今年のクリスマスは、ジーン・アモンズのこのアルバムを聴きながら過ごした。冒頭がSwingin' for Xmasという曲で、もろびとこぞりてやらジングルベルやらをごちゃ混ぜにして豪快に吹きまくっているのが楽しい。後年の、特に「出所」後は、なんというか、任侠の親分的大貫禄を身につけたアモンズだが、すでに若い頃からドスの効いたブロウをかましていて恐れ入るばかりだ。
とはいえ、今日の本題はアモンズではなく、ドラマーのアイク・デイである。例えばピアニストのサディク・ハキムは、『チャーリー・パーカーの伝説』でこう語っている。
ニューヨークにくる以前には、私はシカゴでジェシー・ミラー、それに、ずいぶん若くて死んでしまったアイク・デイというすばらしいドラマーと共に仕事をしていた。このドラマーについては、そのうちマックス・ローチやアート・ブレイキーにきいてみるといい――影響をうけているはずだと私は思うのだ。(p. 157)
ローチやブレイキーがデイについて言及したのは寡聞にして知らないが(ローチがケニー・ドーハムらと一緒にデイの演奏を見ている写真は残っているらしい)、ロイ・ヘインズはどこかで、自分が目にした中で最も優れたドラマーはデイだと語っていた。バディ・リッチも、ジョニー・カースンに史上最高のドラマーは誰かと聞かれ、即座に「アイク・デイ」と答えたそうだ。「世界最高のドラマー」がキャッチフレーズの男にそう言わせるというのは、尋常な力量ではない。
デイの生涯に関してははっきり言ってよく分からないのだが、どうやら1927年の生まれのようである。幼いころから才能を発揮し、16歳からすでにプロとして活動していたようだが、このころからもうヘロイン中毒になっていたと思しい。見事に往年のジャズ的な滅茶苦茶な生活を送ったあげく(そもそもスネア以外ドラム・セットを持っていなかったという)、50年にはボロボロになって半引退状態となり、55年くらいに結核で亡くなった、というのがどうやら最も信憑性のある話で、それ以上のことは今となってはもう分からない。その演奏にしても、ローチやエルヴィン・ジョーンズに先行してポリリズムを駆使した高度なプレイをしていた、という人もいれば、大して技術的には優れていないショウマンだったという人もいて、いよいよ真相は霧の中である。
ジャズの場合、始祖と謳われるバディ・ボールデンを始め、そもそも音源が残っていない「伝説のミュージシャン」が何人かいるわけだが、幸か不幸かデイは数曲の録音が残っている。その中で最も入手しやすいのが、このアモンズのアルバムに収録された二曲(It's The Talk Of The TownとStuffy)なのだった。
と言っても、正直これらの演奏からは、ヘインズやリッチ、あるいはローチやブレイキーといった超一流どころを脱帽させた実力は、ほとんど何もうかがい知ることができない。Stuffyでの即応力溢れるフィルの入れ方に、かろうじてその名残が感じられなくもない、いや気のせいかな、というくらいである。思えば名声などはかないものだが、それはそれとして、演奏自体は素晴らしい。
2011-12-26 [長年日記]
_ [Jazz] The Wailer / Sonny Cox
シカゴ特産のヘンテコなジャズ/ソウル/R&Bを集めた名コンピレーションChicago Soulについてはが、この中に一曲だけ入っていたのがソニー・コックスである。アルト・サックスの音そのものが押しつけがましいというか、不必要に泣きが入っているというか、なかなかの押し出しの良さで大変気に入り愛聴したものだ。ちなみにYouTubeにも音源がありました。聞けば私が何を言いたいのか理解していただけると思う。
で、前出の曲名がタイトルとなった、たぶんコックス名義としては唯一のアルバムがこれなのだが、実に、実に、素晴らしい。なにせずっとこの調子なのである。一応売れ線狙いというか、メロウなことをやりたかったのではないかと思われる節もあるのだが、そもそもあんまりサックスうまくないので、ギラギラしたところ、泥臭さがイヤが応にもにじみ出してしまう。特に掉尾を飾るHoggin'という曲が、タイトルもまあ大概なひどさだが、内容もそれに一歩も譲らない圧倒的な暑苦しさで素晴らしい。リチャード・エヴァンスのアレンジもダサかっこいいの極致と言えよう。
このアルバムが録音されたのは1966年で、その後ミュージシャンとしてのコックスの行方は杳として知れなかったのだが、結局音楽からは足を洗ってそうだ。それも、勝率9割で州大会でも優勝とかいう超優秀なコーチだったようだが、人間的にはいろいろ問題があったらしいあたり、想像通りでなんだかうれしくなる。ジョー・ヘンダーソンと友達だったというのも初耳だったが、「ソニー」がソニー・スティットに由来しているというのも仰天だ(一体どこが似てるんだ?)。何はともあれ、幸せな余生を送ってくれていてよかった。
2011-12-28 [長年日記]
_ [Jazz] Pinnacle / Freddie Hubbard
2011年に出た発掘盤では、これを一番良く聞きましたかねえ。1980年、サンフランシスコ「キーストン・コーナー」におけるライヴで、例によって店主のトッド・バラカンが自分の店の機材で録っていた音源なので、ライン録りにありがちなやや痩せた音ではあるけれど、音質そのものは悪くない。
1980年前後のフレディ・ハバードのレギュラー・バンドは、テナー・サックスにデヴィッド・シュニッター、ピアノにビリー・チャイルズという、地味ながら実力のある連中を擁していて、御大のトランペットも唇にトラブルを抱える前で絶好調という、今から思えば相当凄い陣容だったのだが、なぜかリイシューが進んでいなかったので知名度も低かった。数年前にようやく1981年録音でほぼ同じメンツによるMPS盤Rollin'がCD化されて、あれもなかなか良かったが、このライヴ盤のほうが個人的には好きです。細かいことならいろいろケチはつけられるのだろうが、何と言っても場に流れる空気が華やかなのが良い。レパートリーも、大して代わり映えしないとは言えどれも良い曲ばかりで、今やハバード・クラシックと言ってもよいだろう。One Of Another Kindなんかはほんとにかっこいいですね。ゲスト(飛び入り?)のフィル・ラネリンやハドリー・カリマンもがんばっている。
2011-12-29 [長年日記]
_ [Jazz] Underground Soul / Houston Person
ヒューストン・パースンのデビュー作。かなり前に一度日本でCD化されたものの、まもなく廃盤になってしまった。今やAmazon.co.jpでは若干のプレミアがついているらしい。その割にジャケ写画像すらないわけだが…。本来はこういうジャケである。後年ピアニストや教育者として名を揚げたマーク・レヴィンがトロンボーンで参加しているのだが、氏いわく、「7枚くらいしか売れなかった。うち2枚を買ったのはおれ」。
駄作がほとんど無いパースンらしく、内容はパリっとしていて聴き応え十分なのだが(テンポを落としてじっくり歌い上げるタイトル曲が特に素晴らしい。なぜかエドゥ・ロボの「Aleluia」とかもやっている。曲名の綴り間違えてるけど)、よく分からないのがハモンドオルガン奏者の素性である。そこそこうまいのだが、「チャールズ・ボストン」といういかにも偽名くさい名前で、最初はてっきりボストン出身のレヴィンが二刀流をやっているのかと思ったのだが、オルガンとトロンボーンが同時に音を出しているところが結構あるので、どうもそうではないらしい。ご本人に直接聞いてみたところ、本当にボストンという人だったそうだが、彼はその後どうなってしまったんだろう。
2011-12-30 [長年日記]
_ [Jazz] R.I.P. Odell Brown, 1940-2011
今年はオサマ・ビンラディンから金正日に至るまでさまざまな有名人が亡くなったが、そんな中、5月3日にオーデル・ブラウンがひっそりと亡くなっていたことに気づいた。世間的には無名な人だし全然話題にもならないが、個人的には五指に入るくらい好きなオルガン奏者だったのでちょっと残念である。といっても、ここ20年くらい全く音沙汰がなかったのだが…。
ブラウンと言うととりあえず挙げられるのが「オーデル・ブラウン&ジ・オルガナイザーズ」名義の作品で、例えば1967年に出たこのMellow Yellowはビルボードで173位に達するなど結構なヒットになったらしい。こりゃ売れるでしょうなという感じの軽快でポップな(そしてちょっと今となってはややダサい)演奏がてんこもりで、ドノヴァンのヒットをオリジナルの発表間もなくカバーしたタイトル曲も、定番のマシュ・ケ・ナダも最高のできばえだ。ブラウンのオルガンは、とにかく呆れるくらいに流ちょうでフレーズが歌いまくるところに特長(?)があるのだが、この耳馴染みの良さ、聞いていてラクな感じは、どことなくクレイジーケンバンドを想起させるものがある。ヘンリー・ギヴスンのコンガも例によってキレ味抜群だ。
ジ・オルガナイザーズの売り物はその折々のヒット曲のパクリカバーと2サックス編成だったようで、これは1968年のDuckyでも踏襲される。これがまたやたらに親しみやすい作品で、バカラック・ナンバーのThe Look Of Loveとか、マーヴィン・ゲイ&タミー・テレルのAin't No Mountain High Enoughとか、もうなんだかよく分からないが、歌の無い歌謡曲路線というか、恥も外聞もない選曲でとにかく最高潮である。ゲスト参加のフィル・アップチャーチの太いベースも良い。それにしても、サックスがユニゾンでハモるのって気持ちいいっすねえ。とはいえ、せっかく売れ線を狙ったのに意に反してよほど売れなかったのか、バンド内で何かもめたのか、オルガナイザーズ名義の作品はこれで終わってしまうのだが…。
なお、ブラウンはジ・オルガナイザーズ以外にもいくつか単身でサイドマン仕事を手がけているようだが、その中で特記すべきは(というか、私が聞いたことがあるのは)やはり、ソニー・スティットとバンキー・グリーンが(2アルト・サックスで!)共演したこのSoul In The Nightだろう。これは割と普通にジャズの隠れ名盤であって、特に4曲目のHome Stretchにおける、手と足(フット・ペダル)を存分に駆使したブラウンの大活躍はすごい。ブラウンがちゃんとした技量を備えたジャズ・オルガン奏者であることをはっきりと証明する一曲だ。他もバラードからムード歌謡までバラエティに富んだ曲調で大いに楽しめる。名人スティットはともかく若きバンキー・グリーンの頑張りが光るし、EWF結成前のモーリス・ホワイトが、なかなかかっこいいドラムスを叩いているのも思わぬ拾いもの。
この後のブラウンの活動は、アルバム・アーティストとしては完全に散発的なものになるのだが、一方で伴奏者兼アレンジャーとしてはマーヴィン・ゲイとの付き合いが深まったようで、彼のバックバンドでキーボードを弾くと共に、ゲイの生前最後の大ヒット曲となったSexual Healingの共作者に名を連ねたりもしている。そんな中、1974年にはたぶん最後のリーダー・アルバムとなるI Love Every Little Thing About Youを出すのだが、これがまたジャケの見栄えのしょぼさというかやる気の無さに反比例して死ぬほどメロウな作品で、実に素晴らしい。特に冒頭を飾って11分にも及ぶスティーヴィのあの名曲のカバーは、まさにブラウンの個性にぴったりのはまり具合だ。とはいえ、他の曲では当時の本業を反映してかブラウンはオルガンよりもエレピや生ピアノを弾く局面が多く、ちょっぴり残念ではあるが。
そんなわけで、ブラウンさん別に面識はないけれど、これまで素晴らしい音楽をありがとう。ゆっくりお休みください。マーヴィンの都合もあるので、天国か地獄かどちらかはよく分からないが、またあのあたりの人たちと甘酸っぱいビタースウィートな演奏をせっせと繰り広げていて欲しいものである。音楽を聴く喜びというのは、結局のところそのへんにしかないのだから。
2011-12-31 [長年日記]
_ [Jazz] Storyteller / Jim Hall
1981年のCirclesと1989年のAll Across The Cityをカップリングした2枚組。お買い得な上に両方とも今となっては単体では手に入りにくいのでありがたい。
CD1のCircles相当分は、基本的にホールのギター、ドン・トンプソンのベース、テリー・クラークのドラムスというギター・トリオ編成なのだが、トンプソンは裏芸のピアノも弾く。「も弾く」どころか、1曲目の(All Of A Sudden) My Heart Singsなどでは全面的にトンプソンのピアノがフィーチャーされており、別途ベーシストとしてルーファス・リードが加わっているくらいである。で、この演奏がものすごく爽快でかっこいい。途中急速テンポに切り替わってからが聞きどころ。
私のような雑駁な耳の持ち主にとっては、1枚通してこの調子だったらもっとうれしかったのだが、2曲目以降は、いかにもいつものホールという感じの、エッジを丸くした独特のギターの音色が楽しめる地味でじっくりした演奏。まあ、これはこれで大晦日の夜とかに聞くにはちょうどいいんですけれども…。
CD2のAll Across The CityはCirclesの8年後の作品。ギル・ゴールドスタインのキーボード、スティーヴ・ラ・スピナのベース、テリー・クラークのドラムスというカルテット編成。これまた地味ではあるけれども、都会的洗練の極致みたいな音楽で、かつ音楽的な中身も濃いので、こういうのが好きな人にとってはたまらんのだろうなあ、というのは私でも分かるのだが、一枚通して聞くのは個人的にはちとつらいっす。渋いバーとかでこういうのが静かに流れていたらしびれるかもしれませんね。80年代のキーボードを多用した作品は、今聞くと異様に古くさく感じられて聞くに耐えない場合もあるのだが、ゴールドスタインのキーボードの使い方はつぼを心得た控えめなものなので、今聞いてもあまりズレを感じさせない。












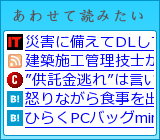

_ mhatta [テスト]