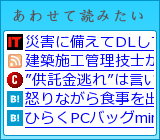2011-10-16 [長年日記]
_ [Jazz] Indian Summer
秋から冬にかけて一時的に気温の高い日が戻ってくるのを日本語では小春日和などと言うが、英語ではそれを「Indian Summer」と言う。今日なんかはまさにそれでしたね。
スタンダード・ナンバーというほど頻繁には演奏されていないような気もするが、Indian Summerというジャズ曲もある。元々1919年にピアノ曲として作曲されたもので、のちに歌詞が付けられた。インディアン・サマーは6月の盛夏、すなわち成就しなかった激しいロマンスがこの世に迷い出た幻、というような歌だったと思うが、この手の寂寥としたラブ・ソングは若い頃のフランク・シナトラの独壇場で、実際この曲を最初に有名にしたのは、シナトラが1940年、当時所属していたトミー・ドーシー・オーケストラで歌ったバージョンだった。
ところで、私が個人的に好きなのは、まずはスタン・ゲッツが吹いたバージョンである。有名なStan Getz Quartetsに収録されているもので、古い録音なので音質は良くないし、わずか3分弱で終わってしまうのだが、テーマの歌い方といいスパっとしたアドリブの切れ味といい最高だ。音の悪さすらも得体の知れない妖気を増す方向に機能している。アル・ヘイグの差し出がましくないピアノもいつもながら良い。
もう一つは、ピアニスト、ジョージ・ウォーリントンのNew York Sceneに収録されているバージョンだ。ウォーリントンと言えばカフェ・ボヘミアでのライヴが超有名で、それで多くの場合話が終わってしまうのだが、引退直前に録音したこの作品もフィル・ウッズやドナルド・バードをフロントに立てたなかなか充実した演奏である。特にこの曲では、バードの余裕綽々としたテーマの吹き回しと、そこに絡みながらソロへと飛び出して行くウッズが発散するのがいかにもハードバップという匂いで、それだけでうれしくなってしまうのだ。全然関係ないが、最後を飾るSol's Ollieという曲も超かっこいい。
最後に、シナトラと並んでこの曲を有名にした一人が1945年に録音したコールマン・ホーキンスなのだが、そのちょうど20年後、亡くなる4年前の1965年に吹き込んだWrapped Tightでもこの曲を再演している。ホークはこのころを境にアル中が悪化し、以降は文字通り気息奄々という感じの悲しい演奏がほとんどになってしまうのだが、このころはまさに人生の小春日和という感じで、威信に満ちた堂々たる吹きっぷりを披露している。大御所最後の傑作と言えるだろう。サイドを固めるバリー・ハリスのピアノがまた渋いのね。