2008-10-16
_ [Rant] 陰謀論とイヤミのうまさ
他人の英語の添削ばかりしていても仕方がないんですが、なんだか目についてしまったので。
Yet while Paul Krugman's talents as a theorist are shared by a handful of his peers, his gifts as a communicator are not. It seems that the Nobel committee felt that Mr Krugman's role as a public intellectual was a stepping stone to the prize, not a stumbling block.
(理論家としてのポール・グルーグマンの才能なら四、五名くらいは共有しているものだから、彼の才能は伝達者かどうかということだ。ノーベル財団としては、公的な知性としてのクルーグマン氏の役割は、受賞の足がかりであって、障害ではなかった。)さらっと読むと褒めているみたいだけど、これって、高度なレトリックによる反語表現っていうことジャマイカ。
別に反語でも何でもないような。というか若干誤訳だよね、これ。「理論家、学者としてのポール・クルーグマンの才能に匹敵する人は何人かいるだろうけど、コミュニケーター、一般向けの啓蒙家としての彼の才能に匹敵する人はいない。」ってことです。public intellectualというのは訳しにくい言葉だが、日本語だと「知識人」というのが一番近い言葉かしらん。全体にfinalvent氏は、どうも「これはイヤミを言っているに違いない」という思い込みが先にあって、そこから妙な解釈を引き出しているように思われる。こう言っちゃなんだが、田中宇さんを思い出した。他にも変な訳はあるんだが、kmoriさんがすでに指摘している。ただkmoriさんの訳もちょっとおかしくて、該当箇所を私が訳すなら
いずれにせよ、ブッシュ批判が書けるジャーナリストはいくらでもいるが、「恒星間貿易の理論」などという珍奇なものを書けるエコノミストは一人しかいないし、論争の才に長けた論客といえども、経済の論理をウィットに富んだ文章で啓蒙できる人となるとそうはいない。
くらいかねえ。ちょっと意訳だけど。
どちらかと言うと今回私が驚いたのは、コラムニスト、クルーグマンを擁する本家本元ニューヨークタイムズの記事だ。身内だし、主張は新聞のカラーとも合っているし、さぞべた褒めしてるんだろうと思ったら、クルーグマン批判で知られるダニエル・クラインのコメントをわざわざ取っていたのね。
「クルーグマンの一般向けの仕事の大半は恥ずべきものだ」と、ジョージ・メイソン大学の経済学教授であるダニエル・クライン氏は言う。彼は今年、クルーグマン氏が本紙タイムズに執筆したコラムの内容を広範囲に検証したレビュー論文を執筆した。「彼は、経済学が大衆迎合的な民主党の気風に反するような結論をもたらす多くの主要な問題を、全く取り上げない。特に彼がニューヨークタイムズに執筆するようになってから、彼はいよいよ民主党に迎合的になっていると私は思う。」
共和党のマケインにほとんど勝ち目がなくて余裕があるということなのかもしれないが、しかし、仮に自紙への寄稿者がなんか賞を取った場合、日本の新聞がご祝儀記事にこんなこと書くかねえ。ちなみに私の印象では、クルーグマンは大して民主党べったりでもないです(マケインよりはましというだけで、オバマもあまり支持していない。たとえばこれ)。
なお、私が知る限り、今回のクルーグマン受賞関係の記事で洋の内外問わず一番イヤミが効いていたのはグレッグ・マンキューだと思う。マンキューも相当偉い経済学者なのだが、クルーグマンのスタンスには以前からやや批判的だ。で、自分のブログでこんなふうに書いていた。
おめでとう、ポール!
この最新のノーベル受賞者についてもっと知るには、ポールの研究上の貢献に関する分析、そして彼の記名コラムに関する分析を読むといいですよ。
字面だけ読むとどうということもないのだが、リンク先を追うと、前者はジョン・ベイツ・クラーク・メダルを取ったときのディキシットの推薦コメント(こちらは普通に褒めてるだけ)、後者はなんと先ほどのクラインの批判論文なのですよ。研究者としては認めるがコラムニストとしてはけしからん、ということなのかしらん。狙ってやってるのか単に勘違いしただけなのか、そこが分からないところがうまい。
2011-10-16
_ [Jazz] Indian Summer
秋から冬にかけて一時的に気温の高い日が戻ってくるのを日本語では小春日和などと言うが、英語ではそれを「Indian Summer」と言う。今日なんかはまさにそれでしたね。
スタンダード・ナンバーというほど頻繁には演奏されていないような気もするが、Indian Summerというジャズ曲もある。元々1919年にピアノ曲として作曲されたもので、のちに歌詞が付けられた。インディアン・サマーは6月の盛夏、すなわち成就しなかった激しいロマンスがこの世に迷い出た幻、というような歌だったと思うが、この手の寂寥としたラブ・ソングは若い頃のフランク・シナトラの独壇場で、実際この曲を最初に有名にしたのは、シナトラが1940年、当時所属していたトミー・ドーシー・オーケストラで歌ったバージョンだった。
ところで、私が個人的に好きなのは、まずはスタン・ゲッツが吹いたバージョンである。有名なStan Getz Quartetsに収録されているもので、古い録音なので音質は良くないし、わずか3分弱で終わってしまうのだが、テーマの歌い方といいスパっとしたアドリブの切れ味といい最高だ。音の悪さすらも得体の知れない妖気を増す方向に機能している。アル・ヘイグの差し出がましくないピアノもいつもながら良い。
もう一つは、ピアニスト、ジョージ・ウォーリントンのNew York Sceneに収録されているバージョンだ。ウォーリントンと言えばカフェ・ボヘミアでのライヴが超有名で、それで多くの場合話が終わってしまうのだが、引退直前に録音したこの作品もフィル・ウッズやドナルド・バードをフロントに立てたなかなか充実した演奏である。特にこの曲では、バードの余裕綽々としたテーマの吹き回しと、そこに絡みながらソロへと飛び出して行くウッズが発散するのがいかにもハードバップという匂いで、それだけでうれしくなってしまうのだ。全然関係ないが、最後を飾るSol's Ollieという曲も超かっこいい。
最後に、シナトラと並んでこの曲を有名にした一人が1945年に録音したコールマン・ホーキンスなのだが、そのちょうど20年後、亡くなる4年前の1965年に吹き込んだWrapped Tightでもこの曲を再演している。ホークはこのころを境にアル中が悪化し、以降は文字通り気息奄々という感じの悲しい演奏がほとんどになってしまうのだが、このころはまさに人生の小春日和という感じで、威信に満ちた堂々たる吹きっぷりを披露している。大御所最後の傑作と言えるだろう。サイドを固めるバリー・ハリスのピアノがまた渋いのね。
2012-10-16
_ [Jazz] Blues Up (Piano Solo) / Dave McKenna
最近寒くなってきたので、地味なソロ・ピアノを好んで聞いている。ソロ・ピアノ特有のしみじみとした味わいがいかにも秋向きである。ジャズにおけるソロ・ピアノは、共演者とのインタープレイというか共創性のようなものが重視されるこの世界では、なんというか労多くして益少ない分野のような気がするのだが(偏見)、ピアニストによってはソロのほうが安心して聞けるという不思議な人もいて、その一人がデイヴ・マッケンナ(本当はマッキーナと読むらしい)である。
ビバップ以前に活躍したオールド・スクールのピアニストたちは皆強靱な左手を持っていて、ベースを含めたリズム・セクションの仕事を一人で全てこなしてしまっていた。アート・テイタム、テディ・ウィルソン、ナット・キング・コール、みんなすごかったですね。しかし、バド・パウエル以降左手の役割が相対的に低下し、しかもピアノ、ベース、ドラムスの分業という近代ピアノ・トリオの定型ができてしまうと、こうしたスタイルではバンド編成で微妙に「弾きすぎ」になってしまう弊害も生じてしまった。ようするに、左手の動きがベース・ラインやドラムスによるリズム・キープとぶつかって、うるさく聞こえてしまうのである。
マッケンナは1930年生まれなので、世代的にはビバッパーにしてもかなり若い部類に入るのだが、スタイルは完全に古き良きスウィングのそれで、この世代としては例外的にかなり強力な左手を持っている。若いだけにモダンなセッティングでもそれほど違和感なく溶け込めるのだが(ズート・シムズのDown Homeとかが好例)、個人的にはソロ・ピアノのほうが落ち着いて聞けるような気がする。これは1955年に録音されたデビュー作で、なんとプロデュースは若き日のクリード・テイラー。初録音からいきなりソロ・ピアノで通すというのは冒険だったはずだが、変化球とはいえマッケンナの資質には合った選択で、さすがテイラーというべき慧眼だと思う(売れたかどうかは知らないけど…)。深みやら凄みやらとは無縁なものの、あくまで平明ながら細かいところまで神経の行き届いた弾きっぷりはとても魅力的だ。
このCDにはおまけとして、1963年のReam盤「Lullabies In Jazz」も併録されているのだが、こちらも全編ソロ・ピアノだし、オリジナルは入手困難と思われるので、かなりお得な気分である。もちろんこちらでも、両手をフルに活かしたマッケンナの至芸が楽しめる。







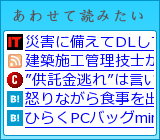

_ ぷくまん [イノベーションが人々を不安に陥れ、プライバシーを侵害することは許されるのか?グーグルストリートビューの話である。勿論..]