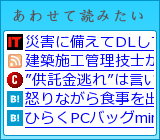2007-05-06 [長年日記]
_ [Obit] エンタツ、ダイラケ、ノック、やすし
ずいぶん昔の話だが、何かのテレビ番組で中田ダイマル・ラケットの漫才を見たことがある。糖尿病かなにかで痩せこけた最晩年のダイマルとラケットが、ひたすらじゃんけんを続けるというネタだった。
小林信彦のような芸に厳しい人に言わせれば、全盛期には遠く及ばないという評価になるのだろうが(天才伝説 横山やすしでは、「ダイマル・ラケットのテレビでの晩年の漫才は、正直にいって、正視できないものであった」と述べている)、繰り出されるイカサマの圧倒的なくだらなさ、怪しい身振り手振り、しつこい反復と絶妙な息の合い方、生まれてこのかたあんなに笑ったことはない。最後の輝きだったのだろうか。言っても信じてくれないだろうからYouTubeにでも映像が無いかなと思ったが、あいにく誰もアップロードしていないようだ。全ては語り口とタイミングの問題に過ぎない、というのは、私がその時のダイラケの漫才から学んだことである。
なんで急に思い出したかというと、横山ノックが死んだからだ。ノックと言えば弟子に横山やすしがいて、やすしはダイラケを崇拝していた。
酒席で晩年のダイラケの漫才をテレビで見ていたノックが、つい「さすがにダイ・ラケ先生も衰えたなあ」と口を滑らせてしまい、それを咎めたやすしが「このハゲ! ダイ・ラケ先生の悪口を言う奴は許さんぞ。ボケ!」とさんざ罵った挙句、ひとりだけ先に帰ってしまったと言う逸話がある。芸事の世界では絶対的な存在であるはずの師匠をつかまえて、ハゲボケ呼ばわりしたやすしも相当なものだが、それでも破門しなかったノックもただ者ではない。
ノックといえば不祥事への対応を間違えて寂しい晩年を送ることになってしまったが、一時は大阪府知事にまで上り詰めた人だ。漫画トリオの他2人をドライに切捨て政治家に転身したノックと、相方きよしに去られたショックからついに立ち直れずにほとんど自殺に等しいような死に方をしたやすしとは、世間的な成功という意味でも一個人としての冷徹さという点でも雲泥の差だが、漫才へのスタンス、もっと言えば漫才というものに対するオブセッションという面では案外近しいところがあったのではないか。
以下も小林の日本の喜劇人に載っていた話で、ちょっと長いが好きな部分なので引用しよう。やはり最晩年の横山エンタツ・花菱アチャコに砂川捨丸を交えてテレビで鼎談させるという、今からすれば相当贅沢なつくりのテレビ番組があり、小林が構成を担当した。エンタツ・アチャコは吉本の商策もあって喧嘩別れのような形で解散して久しく、漫才の再現は無理と思われていたのだが…
私は、二人がスタジオで顔を合わせて「石田(エンタツの本名)」「藤木(アチャコの本名)」と呼び合っていたときから、日常の会話が片っぱしからギャグになってしまうのに呆然としていた。日本語の会話はギャグにならないなどというのは嘘である。まわりにいる本職の漫才師が笑い転げるほど、おかしい。レコードなどでうかがうべくもないタイミングの妙、間、はずし方−−それは、おそらく、もっとも洗練された日本語の会話であった。
漫才が始まると、からだの不自由なエンタツのひたいを、アチャコが叩く。少しも、いたいたしい感じがしない。
横山ノックが狂的な目つきで私に言った。
<あれでこそ、わたしたちの先輩なんです!>
笑いの渦がおさまると、東京のディレクターの声がきこえた。
「リハーサルはこれくらいで…」
「ぼくらの漫才は、リハーサルしたら、あかんのや!」
アチャコが吐き出すように呟いた。
やすしの葬式の弔辞で、ノックは「僕が死んだ時は一緒にネタ合わせして漫才をやろう」と述べたと言う。リップサービスだったのかもしれないが、若干の本音も混じっていたような気がする。やすしはツッコミ的な要素も持ち合わせていたとはいえ、基本は2人ともボケだ。今頃どういう漫才をやっているのか、ちょっと興味がある。