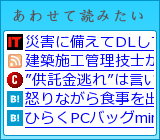2006-05-14
_ [Music] Live at the Jazz Showcase in Chicago / Hampton Hawes
シカゴのクラブ「ジャズ・ショーケース」(1947年開店で未だ健在)における1973年のライヴ。Vol.1と2の2枚が出ている。どうやら元々は正規録音ではないらしく(サウンドボード音源か?)、若干音が痩せていたり割れていたりするのが残念だが、演奏内容そのものはサイドメンの良さも手伝ってハンプトン・ホーズ晩年の傑作と言ってよい出来になっている。少し大きめの音量で聞くとなお良い。後半で三者が突然もの凄い盛り上がりを見せるVol.1のSpanish Moods、シンプルなブルーズにもかかわらず26分以上も弾きまくって飽きさせないVol.2のBlue Bird〜Blue Hampあたりがとりあえずの聞きどころか。ホーズのヴォーカルは止めておいたほうが良かったと思うが…。
ライナーノーツもなかなか興味深い。Vol.1にはプロデューサーのホルスト・ウェーバーが行ったホーズのの結果が収録されているのだが、ミンガスがピアノを弾いたOh Yeah(Charles Mingus)を聞かされて、明らかに誰か分かっているのに「このピアニストは嫌いだ」とか言っている。昔Mingus Three(Charles Mingus)で共演したときにイヤなことでもあったんですかね。アイラーが嫌いというのも意外と言えば意外だった。Vol.2にはやはりウェーバーのホーズに関する思い出話が載っているが、ホーズは元々6本指だった(生まれてからすぐ手術で除去したらしい)というのが驚き。そういう奇形があるのかどうかよく知らないが、もしそのまま12本残っていたらどういうことになっていたんでしょうね。ホーズの死を知らされて、ちょうどウェーバーの元でレコーディングしていた山下洋輔がしたことというのもなかなか心温まるエピソードだ。
_ [Reading] 大山康晴の晩節 / 河口俊彦
昨今のを巡る騒動は、コアでディープな将棋ファンにとっては不愉快なこと甚だしい話ばかりだろう。しかし、私のように将棋に関心を失って久しい人間にとっては、もう一度将棋というものの存在を思い出させてくれたという点でそれなりに意味のある出来事だった。
この本も評判が高いということは知っていたのだが、の事績について大体のことはすでに知っていたし、特に興味も湧かなかった。最近の騒動で多少将棋に関心が戻ってきたのと、文庫になったのとで、ようやく読んでみたという程度である。しかし、読んでみれば実際これは世評通りの優れた評伝であり、大山康晴という不世出の棋士を描くものとしてこれ以上のものがあり得るとは思えない。将棋のルール程度は知っていたほうがより楽しめるだろうが、全く知識が無くても十分に読めると思う。
おそらくこの本のポイントは、大山という人間の描き方だ。人間的にはかように最悪だった、でも将棋はこのように強かった、とあっさり両面を分けてまとめてしまうのはありがちだが、それではつまらない。大山の酷薄で非情な一面、天才ばかりとされる将棋界において、吾人の他に人無しと確信する傲慢さが、いかに彼の強さ、とりわけその図抜けた耐久力に結びついていたかを明らかにしたところに、この本の価値はある。思えば、功罪がはっきり分けられる人間に魅力的な者はいない。功罪が一如となっているからこそ、ある種の深みと力強さが出てくるのだろう。
優れた人物伝を書くには対象を愛すると同時に冷酷に突き放すことが必要なのだが、河口はそれに見事に成功している。小林信彦が渥美清を描いたおかしな男 渥美清 (新潮文庫)(小林 信彦)や、横山やすしを取り上げた天才伝説 横山やすし (文春文庫)(小林 信彦)に匹敵する仕事だと思う。文庫版あとがきによれば升田幸三や塚田正夫、芹沢博文といった面々の評伝も構想しているらしいので、次にも期待したい。
2007-05-14
_ [Reading] 坂口安吾の「全然」
現実逃避に風呂で将棋随筆名作集を読んでいたのだが、最後に坂口安吾の「勝負師」が収録されていた(青空文庫にも入っている)。この随筆は安吾の傑作のひとつであり、また将棋のみならずおよそ競争者の心理をここまで明晰に切り出しえた文章は稀ではないかと思うが、今日の話は残念ながらエッセイの中身とはあまり関係がない。
私が読んでいて驚かされたのは、安吾の「全然」の用法だった。個人的に、「全然」を肯定の強調として使うことに強い違和感がある。ようするに「全然オッケー」とか「全然大丈夫」みたいな言い回しだが、「全然」はあくまで否定の強調という感覚があるのですね。私より若干でも年下になるともう全然違和感を感じないようなので、これは1990年代以降に市民権を得たかなり新しい言い回しなのではないかと思っていた。
ところが、安吾は「全然」をこう使っているのである。
その一回戦は、木村が全然勝つた将棋に、深夜に至つて疲労から悪手の連発で自滅したといふ。
このエッセイが書かれたのは1949年。安吾は言葉を破格に使う人だったから、必ずしも断定は出来ないが、いちおう当時から「全然」を肯定の強調として使う用法は存在したということにはなる。
面白いのは、安吾はこのエッセイ内で3回「全然」を使っているのだが、あとの2回はオーソドックス(?)な使いかたなのだ。
碁のまるまるとふとつた藤沢九段が、全然ねむけのない澄んだ目を光らせて、熱心に説明をきいてゐる。
全然読まない手であるから、木村は面食ふ。
といった具合。こういう話を深追いしてもしょうがないのだけれど、Wikipediaの「全然」のエントリではのっけから「本来『全くを以って然るべき』の意で公用される副詞で肯定にも否定にも用いられるが、近年肯定に用いるのは誤りであると称してたびたび話題になる」と触れている。案外よく知られた話らしい。
さらに、「全然OK」は全然OKかや『全然〜ない』をいぢめるあたりを読むと、実は歴史的、学問的見地からは肯定の強調のほうが「正統的」な用法で、否定の強調にしか使えないという教えられ方をしたのは戦後の一時期だけなのではないかという話まで出てくる。安吾の用法からも分かるように、もともと肯定・否定を問わず単なる強調の意味で広く使われていた「全然」が、なぜ一時期だけ「変調」したのか、興味深いテーマだ。
まあそんなこと言われたって、違和感があるのはどうしようもないんですが。